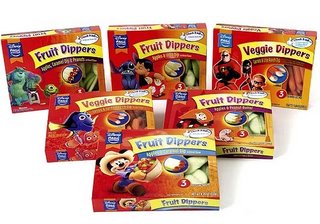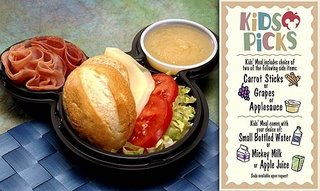ここ数ヶ月アメリカのオーガニック産業で大きな問題として出現をしてきたのは、オーガニックの定義そのものだ。オーガニックの定義の中に、従来だったら考えられなかった、より厳しい基準が求められ始め、活動家たちは、今までのオーガニックを数段厳しいところまで引き上げた。その定義というのは、牛乳の生産に関わる定義の中で、乳牛の扱いがどのようなものかをいうものだった。乳牛が、牛舎に閉じ込められ、牧草地での運動もできず、ただ単に乳牛として機械的に働かされているということが活動家たちの攻撃の矛先になった。大手になってきた、オーガニック牛乳メーカーが、生産効率を求めるが故に、乳牛たちの人道的な扱いを忘れていることへ、活動家たちは怒りを向けた。
ここ数ヶ月アメリカのオーガニック産業で大きな問題として出現をしてきたのは、オーガニックの定義そのものだ。オーガニックの定義の中に、従来だったら考えられなかった、より厳しい基準が求められ始め、活動家たちは、今までのオーガニックを数段厳しいところまで引き上げた。その定義というのは、牛乳の生産に関わる定義の中で、乳牛の扱いがどのようなものかをいうものだった。乳牛が、牛舎に閉じ込められ、牧草地での運動もできず、ただ単に乳牛として機械的に働かされているということが活動家たちの攻撃の矛先になった。大手になってきた、オーガニック牛乳メーカーが、生産効率を求めるが故に、乳牛たちの人道的な扱いを忘れていることへ、活動家たちは怒りを向けた。かなり前にも書いたが、ホールフーズスーパーが、活ロブスターの販売を中止したということがあった。これもロブスターが非人道的な扱いを受けているとして、人道的な扱いができるようになるまで、販売を取りやめるというのがホールフーズの立場だ。水槽で動きを制限されているロブスターを見ていて、ビーガンであるホールフーズのジョンマッキー社長は何かを感じたのだろう。
日本の捕鯨問題にしても、日本不買運動まで行ってしまったアメリカ人活動家。ツナ缶にしてもマグロの捕獲のときに一緒に捕獲されるイルカを守る方式をとらない漁業をしているメーカーのボイコットなど、事例が事欠かない。また、発展途上国の社会ピラミッドの最下層にある農業生産関係の人々、(例えばコーヒー豆などのピッカーたち)の救済を求めるフェアトレードなどなどこれまで、一部の先鋭的な活動家の活動目標だったようなことが、どうでも良いではないかということが徐々に大手リテーラーが無視し得なくなるような事態となってきている。もちろん、どうでも良くないのだが、日本の消費者だったら、これが大手の販売政策にまで影響するような事態には持っていくとは考えにくい。消費者も冷めているのかもしれない。
ただ、どちらが仕掛けているのか判らなくなる事態をニューヨークタイムズは報道している。つまり、その先鋭的な活動家のテーマをちゃっかり借用してホールフーズは人道的に飼育された家畜であることを積極的にラベルで打ち出している。そのために他のディストリビューターやリテーラーとの違いを打ち出し、プレミアムを付けて豚肉や鶏肉を売り始めているという。殺されるのは殺されるのだが、人道的に飼育されたことが消費者の間で付加価値になってきているのだ。
確かにストレス下で飼育された動物を食するのはどのようなものか、今まで考えても見なかったことだが、それが一つの社会価値観になりつつあるのだろう。ロハスは人間だけの基準ではなくなるのだろうか?いろいろと考えさせられるものは多い。